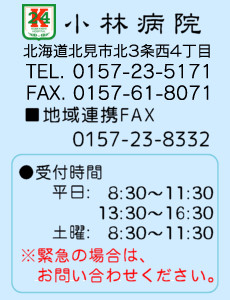トップ » 診療科・センターのご紹介 » » 循環器科 » 循環器科(心臓血管外科、循環器内科)
循環器科(心臓血管外科、循環器内科)
診療内容・主な疾患

当科においては、循環器内科及び循環器外科についていずれの診療も担当しております。
内科的には投薬対症治療のほか、冠動脈疾患に対するカテーテルをはじめとする諸検査及びPCI(経皮的冠動脈インターベンション)治療などを行っております。
外科的には末梢動脈閉塞症に対する血行再建術、動脈瘤切除や動脈バイパス移植なども行っております。
また、人工透析センターにおいて血液透析にも対応しております。
将来的には、開心術にも視野に据えて進めてまいりたいと考えております。
| ■札幌医科大学第2外科 | ||
| 川原田修義 教授 | ||
※経験豊富な専門医が毎週来院し、外来診療及び人工透析の体制をバックアップしております。また動脈瘤等の心臓・血管系の手術も実施しております。
外来担当
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 循環器科 人間ドック 人工透析 |
午前 | 石川 部長 | 川原田教授 (各月変動) |
田畑 部長 | 田畑 部長 | 石川 部長 | (手術・病棟) |
| 呼吸器医師 (第3.4週) |
|||||||
| 午後 | 田畑 部長 | 川原田教授 (各月変動) |
石川 部長 | (循環器心カテ) | (手術) | ||
| 呼吸器医師 (第3.4週) |
|||||||
※変更になる場合がありますので、「循環器科からのお知らせ・代診・特別外来医師のお知らせ」をご確認ください。
入院について
エアコン付き個室を完備、術前術後において快適な入院療養生活環境を提供しています。
医師の紹介
 |
循環器内科部長 石川 浩(Hiroshi Ishikawa) |
||||||||
|
|||||||||
 |
循環器外科部長 第二病院長補佐 田畑 哲寿 (Akihiro Tabata) |
||||||||
|
|||||||||
診療のご案内(循環器科)
高血圧症
高血圧症とは、日本高血圧学会治療ガイドラインによると、収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上を示すものとされています。この場合、運動時や緊張時などの一過性の高血圧状態は除外されますので、平均的に高血圧状態が持続している状態を指しています。
高血圧症は本態性高血圧と二次性高血圧とに区分され、その90%以上は本態性高血圧が占めています。
(1)本態性高血圧
本態性高血圧の原因は明らかではありません。遺伝的因子と環境的因子が複雑に関連して発症するとも云われています。
治療は、血管障害(動脈硬化など)の発症・進行を抑制し、心血管疾患の発症の予防を目的として行われます。食事療法(食塩制限、脂質制限、アルコール制限など)、減量(肥満者の場合)、運動療法、禁煙などの生活習慣の改善に努めることが、降圧剤服用などの薬物療法の効果を大いに増強します。
(2)二次性高血圧
二次性高血圧は明かな原因疾患があって発症すると考えられていますので、原因疾患を正しく診断することが重要で、腎血管性高血圧、原発性アルドステロン血症、褐色細胞種、腎実質性高血圧、等があります。バイパス手術や腫瘍摘出手術などを行うことにより完治が期待される場合があります。
不整脈
不整脈とは、心拍数や脈拍数が一定ではない状態のことを指しますが、心拍数や脈拍数が一定でも、心電図に異常がある場合には不整脈とされます。治療の必要の無い不整脈もあります。
(1)致死性不整脈
心静止、心室細動、伝導収縮解離などがあり、死に至る緊急の状態です。
速やかな心肺蘇生及び除細動が必要です。
(2)頻脈性不整脈
上室性頻拍、心室頻拍、心房細動・心房粗動などについては、症状に応じて不整脈用剤の
注射を行うことがありますが、血行動態に悪影響を及ぼすケースについては、緊急処置が必要な場合があります。期外収縮などについては、経過観察あるいは投薬治療の場合があります。
(3)徐脈性不整脈
室室ブロック、洞機能不全症候群、徐脈性心房細動などについて、ペースメーカー植込み手術を行う場合があります。
当院では、紹介患者を含め年間約30例ほどのペースメーカー植込み術を行っております。
またペースメーカー植込み後の経過観察は、毎月第二、三水曜日の午後に集中的に行っております。
虚血性心疾患
心臓の筋肉(心筋)は冠動脈と呼ばれる血管により酸素や栄養を供給されて収縮運動をしています。
この冠動脈が狭窄や閉塞することにより心筋への血液の流れが悪くなり、その結果心臓に障害が
生じる病気を総称して「虚血性心疾患」と呼ばれており、狭心症や心筋梗塞などが含まれます。
原因としては、冠動脈の血管の内壁にプラーク(粥腫)などが沈着して蓄積していくこと等が挙げられ、高血圧症、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病に起因する動脈硬化症との密接な関係が明らかになっています。
●狭心症と心筋梗塞について
(1)狭心症
冠動脈が狭くなって血液の流れが不足しているもので、一時的に血液の流れが止まって発作を起こしたりします。心筋梗塞の前段階と言えます。主な症状としては、胸部痛や胸部圧迫感などがあります。
(2)心筋梗塞
冠動脈の狭窄が著しかったり、完全に閉塞していたりして血流がストップすることにより心筋が壊死した状態を指いいます。壊死した心筋は当然働かなくなるため、壊死した心筋の範囲によっては生命をも左右する恐ろしい病気と言えます。主な症状は狭心症と同様ですが、痛みの程度や持続時間は狭心症よりも重篤になることが多くなります。
(3)診断と治療
当院では、まず心電図検査を行って異常の有無を調べますが、心電図変化が出にくい場合もありますので、血液検査や心臓超音波検査、心臓の3D-CT(64スライス)を行いながらより詳細に調べます。狭心症あるいは心筋梗塞の疑いがあった場合には、心臓カテーテル検査を行い冠動脈の造影検査を行い、血管の狭窄の程度を調べたうえで治療方針の決定に役立てます。
また、心臓カテーテル検査は診断とともに治療を兼ねることが多くあります。狭窄部位を風船型カテーテルで拡張したり、再狭窄の予防のためステントと呼ばれる金属製の筒状の器具を留置したりして血流の確保を行います。
当院においては循環器内科の医師が中心となり、豊富な経験を生かして検査及び治療を行っております。年間にして約150例に及ぶ症例の検査と治療を行っております。また開心術の適応となれば、札幌医大の心臓血管外科などの関連先進医療施設に責任をもって紹介いたします。
狭心症や心筋梗塞は生活習慣病に起因する動脈硬化と関係があるため、治療には日常生活習慣の改善が欠かせません。運動療法や食事療法、薬物療法などを組合せて治療します。
特に、血管を収縮させる喫煙は厳禁となります。
慢性動脈閉塞症
末梢動脈の狭窄・閉塞性疾患としては、閉塞性動脈硬化症とバージャー病などが挙げられますが、近年は食生活の欧米化や人口の高齢化などに伴って動脈硬化に起因する閉塞性動脈硬化症(ASO)の増加が著しく、慢性動脈閉塞症のうちの大多数を占めるようになりました。
●閉塞性動脈硬化症(ASO)
動脈硬化とは、動脈血管の内壁にコレステロールなどの物質が沈着してプラーク(粥腫)と化し、やがて動脈血管は弾力を失い、硬くそしてもろく変化していったた状態を指します。
動脈硬化は全身の血管に起こりますが、閉塞性動脈硬化症は特に下肢の動脈(大動脈下部~大腿動脈)によくみられる血行障害で、足のしびれ、痛み、冷感などの症状があらわれます。
検査については、症状に応じてABI、CTやMRI、超音波ドップラー、動脈造影などが行われます。
治療については、日常生活習慣の管理、食事療法、運動療法などに加え、薬物療法、外科的手術(バイパス術など)が行われます。
当院では、ASOと診断された場合には積極的に血行再建術を行っております。昨年は腹部大動脈瘤の手術を含め、約20例の実施実績があります。
シャントのトラブル
オホーツク圏内には、12箇所の血液透析施設があります。全施設で約1,000名に及ぶ慢性腎不全の患者が血液透析を受けております。
透析患者に作られたシャント(動脈と静脈を繋いだ本来とは別ルートの血管)が、長期間使用中に何らかの理由で閉塞し、血液透析の実施が不可能になることがあります。
数多くの症例を経験している当院には、心臓血管外科専門医が2名常勤しております。シャントトラブルに適切に対処、治療すべくシャントトラブル外来を開設することといたしました。
現在まで数多くの施設よりシャントトラブルの患者が紹介されてきております。血行再建術後は紹介元の施設において血液透析を継続していただいております。